今テク昔デザイン ― 2015年04月06日 10:13
「今の技術を昔懐かしいデザインでパッケージ」のLED電球「Siphon」です。
パッケージ。
「Edison」は発明当時の雰囲気をイメージしているのでしょう。
フィラメント回りの造作。オレンジ色の棒状のものの中に小さなLEDが並べられています。
ガラスの内側にうっすらと金色の蒸着(風?)の着色が。
色温度2200Kはかなり黄色いですね。LED自体はもっと白いのかもしれません。
こちらは本当に古い(1940年代)真空管(RCA 2A3)のフィラメント回りの造作。左下にちらっと見える金属の蒸着は残留酸素を吸着するためのものです。戦勝後の豊かなアメリカの職人さんは良い仕事しています。いつ見ても綺麗だなぁ。
ところで、家具では意匠権が切れたプロダクトをリメイクするのは定着していますし、車や家電ではレガシーデザイン、レトロデザインは少なからず人気です。
モジュール化、オープンソース化、EV化などを背景にして、ベンチャーや中小規模のメーカーが「今テク昔デザイン」の商品開発にチャレンジする流れが、家具や自動車等に続いて定着するのでしょうか、、注目しています。(既には懐かしいデザインのEVバイクが出てきていますね。)
改めて私が「今テク昔デザイン」に価値があると思いますのは、、
・長く愛されるデザインを広く活用して残す
・低コストで良質の製品を提供
・高齢者や異文化圏の受容性
低コストとは「オープンソース」「モジュール」とともに「もととなるデザインがある」ことが(特に小規模開発においては)開発コストを圧縮することを指しています。もちろんザイン開発が不要ということではなく、スタートラインのアドバンテージがあるということですね。
高齢者や異文化圏の受容性とは、「昔ながらのあり方・使い方」が受け入れやすいと言うことです。どちらも「習慣」が重要な意味を持っていますが、既に知られている物には抵抗が低くなると期待出来ます。これは同時にUIを今テクに置き換える難しさを含んでいます。(例えば黒電話風のスマートフォンに無理があるように)UIを今テクに置き換えるのは丁寧な作業が必用ですね。
Siphonに話を戻しますと、何かのレプリカではなく、ムラッ気のある手仕事感や色づくりなど、「懐かしさ」を本物よりもイメージに従って少しオーバー気味に演出している感じがしますね。それは一つのあり方なのでしょう。
再始動、します。Spoon&Fork ― 2015年02月03日 19:16
2010年、ひとつの出会いから始まったプロジェクトがありました。
沢山の方に助けられて、試作ができ、ご好評を博したのにも関わらず力及ばずに製品化出来ず、、。
その後も何度か消えかかったのですが、その都度助けて下さる方が現れ、ついに製品化の道筋がたちました。
今年の前半には、正式なリリースをさせて頂けると思います。
もう嬉しくって、CGを披露いたします!(笑
過去記事:試作が出来ました!「free x FREE スプーン&スプーンフォーク」
http://dmc.asablo.jp/blog/2011/10/04/
沢山の方に助けられて、試作ができ、ご好評を博したのにも関わらず力及ばずに製品化出来ず、、。
その後も何度か消えかかったのですが、その都度助けて下さる方が現れ、ついに製品化の道筋がたちました。
今年の前半には、正式なリリースをさせて頂けると思います。
もう嬉しくって、CGを披露いたします!(笑
過去記事:試作が出来ました!「free x FREE スプーン&スプーンフォーク」
http://dmc.asablo.jp/blog/2011/10/04/
大変ご無沙汰しておりますm(__)m ― 2014年11月18日 17:22
4月より半年以上の間、更新しておりませんでしたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
(と申し上げてご覧になってらっしゃる方は皆無かと思われますが・・・)
昨年の7月以降更新回数が減り、ここ半年更新がなかったのはひとえに私の能力の限界でした。いつも読んでるよと励まして下さった方、声には出さずとも関心を寄せて下さっていた方には大変申し訳ありませんでした。
申し開きをさせて頂きますと、私は母の最期に付き合っておりました。一月前の今日、自宅にて見送るまでの一年あまり、とても大切な時間を過ごしました。またデザイナーとしても一人の人間の晩年に寄り添う機会を得たことはかけがえのない経験だったと思います。その間にたどり着いた知見や絞った知恵は、ごくプライベートなものではありますが、明示的にもまた暗示的にも、これからのデザインの中に染み出していくことと思っています。
そして明日はこのブログ開設から丸6年になります。お伝えしたいことをまた少しづつ書いて参りますので、あらためまして、よろしくお願い申し上げます。
(と申し上げてご覧になってらっしゃる方は皆無かと思われますが・・・)
昨年の7月以降更新回数が減り、ここ半年更新がなかったのはひとえに私の能力の限界でした。いつも読んでるよと励まして下さった方、声には出さずとも関心を寄せて下さっていた方には大変申し訳ありませんでした。
申し開きをさせて頂きますと、私は母の最期に付き合っておりました。一月前の今日、自宅にて見送るまでの一年あまり、とても大切な時間を過ごしました。またデザイナーとしても一人の人間の晩年に寄り添う機会を得たことはかけがえのない経験だったと思います。その間にたどり着いた知見や絞った知恵は、ごくプライベートなものではありますが、明示的にもまた暗示的にも、これからのデザインの中に染み出していくことと思っています。
そして明日はこのブログ開設から丸6年になります。お伝えしたいことをまた少しづつ書いて参りますので、あらためまして、よろしくお願い申し上げます。
家に帰ろう・流星ワゴン ― 2014年01月07日 15:43
年末年始の読書はこの2冊でした。
「流星ワゴン」は人生に失敗した父親がステップワゴンに乗った幽霊父子との交流を通じて人生に希望を見いだすまでのファンタジーで、評判通り面白かったです。
「家に帰ろう」は終末期を家で過ごした方々の実話集で、いずれも希望に満ちていて家族中が涙しました。
たまたまの組み合わせでしたが、ともに生死と家族の結びつきについて感じさせるものでした。
また(これは個人的な経験を通して感じていたことでもありましたが)死そのものが悲劇ではないということもまた少し理解出来たように思います。
ところで「家に帰ろう」で紹介されたように、社会的入院を止めて自宅(または終末医療施設)で最後を迎えることは確実にトレンドになるでしょうね。デザインすべき事は山積みです。
「流星ワゴン」は人生に失敗した父親がステップワゴンに乗った幽霊父子との交流を通じて人生に希望を見いだすまでのファンタジーで、評判通り面白かったです。
「家に帰ろう」は終末期を家で過ごした方々の実話集で、いずれも希望に満ちていて家族中が涙しました。
たまたまの組み合わせでしたが、ともに生死と家族の結びつきについて感じさせるものでした。
また(これは個人的な経験を通して感じていたことでもありましたが)死そのものが悲劇ではないということもまた少し理解出来たように思います。
ところで「家に帰ろう」で紹介されたように、社会的入院を止めて自宅(または終末医療施設)で最後を迎えることは確実にトレンドになるでしょうね。デザインすべき事は山積みです。
軽さは正義2 高橋工芸のマグ ― 2013年10月29日 15:31
以前、曲げわっぱのカップをご紹介しましたが、軽量木製のカップということで、もうひとつこちらをご紹介いたします。
高橋工芸「Kami マグカップ」、素材は栓(せん)で、49グラムと軽いです。
把っ手部分は貼りです。
曲げわっぱの杉の香りは暖かいものを飲むのに向いていませんでしたが、こちらは主張が弱く気になりません。母(89歳)はお茶を飲むのにもこちらを好んで使うようになりました。
伝統工芸+デザイナーの、奇を衒わない良いもの。好きです。
過去記事:軽さは正義 栗久のリングカップ
軽さは正義 栗久のリングカップ ― 2013年10月02日 15:41
大館曲げわっぱの有名ブランド「栗久」のリングカップです。
わすか27gと驚愕の軽さ。
滑り落とさないようにと付いているリングがアクセントになっています。
この覗いた時の感じ、杉の木目と僅かな残り香がいいですねぇ。
先日はMario Luca Giustiの樹脂製グラスを紹介しましたが、これもお年寄りの日常使いにいいです。
やっぱり「軽さは正義」ですね。
ただ、、暖かいものを入れると杉と塗装の匂いがやや目立ってしまいますねぇ。
せっかく断熱性の高い器(熱湯でもリングを持てば熱くありませんでした)ですので、匂いをしっかり落として、湯飲みとしても使ってみようと思います。
「100歳の美しい脳」 ― 2013年10月01日 23:56
原題の「Aging with Grace.」輝かしく老いる、という意味でしょうか。図書館で借りて読み、そのあと、中古を探して買いました。
大勢の修道女を長期間にわたって調査したスノウドン医師の有名な「ナン・スタディ」について書かれた本です。長期間同じような生活をしたシスターたちの健康状態を追跡し、アルツハイマー病の治療と予防に役立てようと言う研究です。
日本語タイトルにある「100歳の美しい脳」とは、死後解剖で100歳にして全く病変のなかったシスターの例についてです。その他、脳には明らかな病変があるにも関わらず発症しなかった例など興味深いエピソードが書かれています。
調査から浮かび上がるのはアルツハイマーの様々な要因や仮説に対する示唆と、長寿で健やかな老いと若い頃の精神活動とは深い相関関係を示す事です。
特に、20歳頃に書かれた自伝を分析すると、アルツハイマーの発症をある程度予測出来る(自伝の文章と発症率に相関関係がある)ということ。「意味密度の高い」「複雑な」文章を書いているほど発症率が低かったそうです。
また、感情表現が豊か(ポジティブな方が良いかどうかはまだ不明)な方が長命である事も判りました。
ここから著者は子供に対する読み聞かせを推奨しています。これは子供に関わる人には特に示唆に富む内容でしょう。
葉酸やリコピンなど可能性のある栄養素についても言及していますが、それは「葉酸さえ摂取すれば病気にならない」といった単純な話ではないようです。
また、研究者らしい懐疑的な態度は崩さずに、ここでも「最晩年の生きる希望」について書かれていました。
心豊かに前向きに生きるということは、そのまま魂の強さなのでしょうね。
大勢の修道女を長期間にわたって調査したスノウドン医師の有名な「ナン・スタディ」について書かれた本です。長期間同じような生活をしたシスターたちの健康状態を追跡し、アルツハイマー病の治療と予防に役立てようと言う研究です。
日本語タイトルにある「100歳の美しい脳」とは、死後解剖で100歳にして全く病変のなかったシスターの例についてです。その他、脳には明らかな病変があるにも関わらず発症しなかった例など興味深いエピソードが書かれています。
調査から浮かび上がるのはアルツハイマーの様々な要因や仮説に対する示唆と、長寿で健やかな老いと若い頃の精神活動とは深い相関関係を示す事です。
特に、20歳頃に書かれた自伝を分析すると、アルツハイマーの発症をある程度予測出来る(自伝の文章と発症率に相関関係がある)ということ。「意味密度の高い」「複雑な」文章を書いているほど発症率が低かったそうです。
また、感情表現が豊か(ポジティブな方が良いかどうかはまだ不明)な方が長命である事も判りました。
ここから著者は子供に対する読み聞かせを推奨しています。これは子供に関わる人には特に示唆に富む内容でしょう。
葉酸やリコピンなど可能性のある栄養素についても言及していますが、それは「葉酸さえ摂取すれば病気にならない」といった単純な話ではないようです。
また、研究者らしい懐疑的な態度は崩さずに、ここでも「最晩年の生きる希望」について書かれていました。
心豊かに前向きに生きるということは、そのまま魂の強さなのでしょうね。
自立度の変化パターン ― 2013年09月10日 13:06
ここのところこの話題ばかりで恐縮ですが、年齢を重ねると自立度がどのように変化するか、というグラフです。新田國夫著「安心して自宅で死ぬための5つの準備」の91ページから転載しました。(秋山弘子先生の調査結果から)
上下が自立度、左右が年齢です。自立度の変化にはパターンがあり、比較的早い年齢(60歳代)で自立度が下がる方が10〜20%いらっしゃる一方で、75歳まで自立度が下がらない方が男女とも80%以上。多くは元気に暮らしていらっしゃいますね。特徴的な事は男性の10%が90歳を超えても自立度が下がらないこと。
全体には女性の方が長生きで、時々元気なおじいちゃんがいらっしゃる。これは周囲を見回した実感とも合致しています。
もちろん統計的な話しなのですが、60代の山を無事越えれば人生の最終盤まで少しづつ自立度を下げながら生活する事が出来る、と見てとれますね。
先日の「気持ちよく人生の坂を下るための」「ライフアドベンチャーギア」というコンセプトは、この自立度のゆっくりとした下り坂を、気持ちよく生活するためのモノという意味に他なりません。
ここ、デザインしていきましょう。
過去記事:「気持ちよく人生の坂を下る」
http://dmc.asablo.jp/blog/2013/09/02/
過去記事:ライフアドベンチャーギア(または家電)
http://dmc.asablo.jp/blog/2013/09/04/
過去記事:メメント・モリ「安心して自宅で死ぬための5つの準備」
http://dmc.asablo.jp/blog/2013/08/26/
上下が自立度、左右が年齢です。自立度の変化にはパターンがあり、比較的早い年齢(60歳代)で自立度が下がる方が10〜20%いらっしゃる一方で、75歳まで自立度が下がらない方が男女とも80%以上。多くは元気に暮らしていらっしゃいますね。特徴的な事は男性の10%が90歳を超えても自立度が下がらないこと。
全体には女性の方が長生きで、時々元気なおじいちゃんがいらっしゃる。これは周囲を見回した実感とも合致しています。
もちろん統計的な話しなのですが、60代の山を無事越えれば人生の最終盤まで少しづつ自立度を下げながら生活する事が出来る、と見てとれますね。
先日の「気持ちよく人生の坂を下るための」「ライフアドベンチャーギア」というコンセプトは、この自立度のゆっくりとした下り坂を、気持ちよく生活するためのモノという意味に他なりません。
ここ、デザインしていきましょう。
過去記事:「気持ちよく人生の坂を下る」
http://dmc.asablo.jp/blog/2013/09/02/
過去記事:ライフアドベンチャーギア(または家電)
http://dmc.asablo.jp/blog/2013/09/04/
過去記事:メメント・モリ「安心して自宅で死ぬための5つの準備」
http://dmc.asablo.jp/blog/2013/08/26/
2020年の東京、2025年の私たち ノーマライゼーション ― 2013年09月09日 23:35
2020年、東京五輪開催が決定しました。
既に多くの方がパラリンピックを機会に、バリアフリーな東京、世界の範たる東京をとおっしゃっています。私もそうであって欲しいと切に思います。
ここで2020年の日本を確認いたしますと、65歳以上の方が29.1%(高齢化率)、14歳以下が11.7%、です。
10人のうち3人が高齢者というのをイメージする時、地域差もありますが、いわゆる「お年寄り」が増えるというのは違いそうです。
男女とも80%以上の方が75歳までは壮麗であることが判っていますので、現在活動的な方がそのままその年齢になると考えた方が自然ですね。
一方でその5年後の2025年は、高齢化率は30.3%と僅増ですが、団塊の世代の方々がすっぽり75歳以上になります。(2025年問題)ここから、自立度が下がった人が増えて行きます。街のカフェや映画館などで、周囲には車椅子の方が必ずいらっしゃる、というような状況がうまれてきます。健常な方も様々な自立度の方も普通に混在する社会なのです。この時、自立度によって差別される事のないような状況がなければ、実質的にとても住み難い街になってしまうでしょう。このような自立度によって差別される事のない社会作りを「ノーマライゼーション」と呼ぶそうです。
ノーマライゼーションが進んだまちづくりは、パラリンピックにももちろん向いている事でしょう。2020年の東京は「ノーマライゼーション」の理想をぜひ、追いかけて頂きたいと思っています。
WIKI:ノーマライゼーション
http://ow.ly/oPBO2
既に多くの方がパラリンピックを機会に、バリアフリーな東京、世界の範たる東京をとおっしゃっています。私もそうであって欲しいと切に思います。
ここで2020年の日本を確認いたしますと、65歳以上の方が29.1%(高齢化率)、14歳以下が11.7%、です。
10人のうち3人が高齢者というのをイメージする時、地域差もありますが、いわゆる「お年寄り」が増えるというのは違いそうです。
男女とも80%以上の方が75歳までは壮麗であることが判っていますので、現在活動的な方がそのままその年齢になると考えた方が自然ですね。
一方でその5年後の2025年は、高齢化率は30.3%と僅増ですが、団塊の世代の方々がすっぽり75歳以上になります。(2025年問題)ここから、自立度が下がった人が増えて行きます。街のカフェや映画館などで、周囲には車椅子の方が必ずいらっしゃる、というような状況がうまれてきます。健常な方も様々な自立度の方も普通に混在する社会なのです。この時、自立度によって差別される事のないような状況がなければ、実質的にとても住み難い街になってしまうでしょう。このような自立度によって差別される事のない社会作りを「ノーマライゼーション」と呼ぶそうです。
ノーマライゼーションが進んだまちづくりは、パラリンピックにももちろん向いている事でしょう。2020年の東京は「ノーマライゼーション」の理想をぜひ、追いかけて頂きたいと思っています。
WIKI:ノーマライゼーション
http://ow.ly/oPBO2
「子供に戻る」 ― 2013年09月06日 23:13
日本の統計では7割の人が75歳を過ぎると自立度が少しづつ下りながら晩年を過ごします。
自立度の下り方は各個人によって様々だと思いますが、幾つかのパターンには整理出来る事でしょう。
その中で、私自身が着目しているひとつは「認知」の部分の変遷です。2025年を念頭に置くと、どの様な作法をその機器に採用すべきかという課題に仮説が見いだせるのではないか、という思いがあります。
ざっくりと言いますと、一般的に15歳から25歳までの10年を核とした青春期に触れた文化、文明、それを支える技術とその作法は、一生を通じて失われにくいよう(エビデンスなし)なので、そこは一つの基準となるでしょう。
しかし、認知が失われて行くと、10代前半に獲得したであろう作法も失ってしまうようなのです。
例1:儀式(葬式)の進行がどの宗派か判らない修道女。
例2:ライターで線香に火を着ける際、火の先端ではなく根本にあててしまう元喫煙者。
1の例では、儀式である事は判り、2では火をつける事はできますので、「細部」や「コツ」を失っているようにも見えます。概要が判るのに細部が判らないというのはそれ自体は問題は少なそうですが、そこに主体者(行為を行う者)として関わると、混乱してしまいます。小さな混乱は大きな混乱を呼び、事故のリスクを上げてしまいます。
認知症が進んだ個人に何か機器の操作をさせることはない、とお思いの方も多いと思いますが、例えばトイレで用をたす、という身近な行為でも手順を分解すると複雑なのです。トイレは在宅医療の自動化には重要な場所で、そこに設置される機器に対してどのように認知し、関わる場合はどうすべきかは、絶対にないがしろには出来ない課題です。
これらは私の見識よりも遥かに医療面からの研究が進んでいると思います。しかしながら、デザインへの応用という意味ではこれからだと思います。
そこで、一つの着目として、「老い」が「成長」の逆行であるならば、老いを「子供に戻る過程」と捉えるというのがありそうです。
ちょっと乱暴なのですが、この見方だと参考になる事例も多いので、「補助線の一つ」として意識して見ようと思います。
自立度の下り方は各個人によって様々だと思いますが、幾つかのパターンには整理出来る事でしょう。
その中で、私自身が着目しているひとつは「認知」の部分の変遷です。2025年を念頭に置くと、どの様な作法をその機器に採用すべきかという課題に仮説が見いだせるのではないか、という思いがあります。
ざっくりと言いますと、一般的に15歳から25歳までの10年を核とした青春期に触れた文化、文明、それを支える技術とその作法は、一生を通じて失われにくいよう(エビデンスなし)なので、そこは一つの基準となるでしょう。
しかし、認知が失われて行くと、10代前半に獲得したであろう作法も失ってしまうようなのです。
例1:儀式(葬式)の進行がどの宗派か判らない修道女。
例2:ライターで線香に火を着ける際、火の先端ではなく根本にあててしまう元喫煙者。
1の例では、儀式である事は判り、2では火をつける事はできますので、「細部」や「コツ」を失っているようにも見えます。概要が判るのに細部が判らないというのはそれ自体は問題は少なそうですが、そこに主体者(行為を行う者)として関わると、混乱してしまいます。小さな混乱は大きな混乱を呼び、事故のリスクを上げてしまいます。
認知症が進んだ個人に何か機器の操作をさせることはない、とお思いの方も多いと思いますが、例えばトイレで用をたす、という身近な行為でも手順を分解すると複雑なのです。トイレは在宅医療の自動化には重要な場所で、そこに設置される機器に対してどのように認知し、関わる場合はどうすべきかは、絶対にないがしろには出来ない課題です。
これらは私の見識よりも遥かに医療面からの研究が進んでいると思います。しかしながら、デザインへの応用という意味ではこれからだと思います。
そこで、一つの着目として、「老い」が「成長」の逆行であるならば、老いを「子供に戻る過程」と捉えるというのがありそうです。
ちょっと乱暴なのですが、この見方だと参考になる事例も多いので、「補助線の一つ」として意識して見ようと思います。













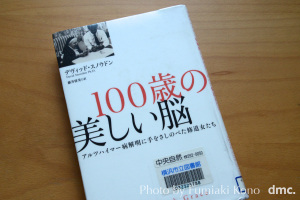



最近のコメント