プラントハンターの仕事「紅茶スパイ」 ― 2012年02月17日 23:59
ツイッターでご縁があったsawaromaさんに紹介して頂いたサラ・ローズ著「紅茶スパイ」読了しました。
1ヶ月ほどかけて読みましたが、ノンフィクションはいつにもまして時間が掛かってしまうので、私にしては速かったと思います。
19世紀半ば、清とイギリスはアヘン戦争を戦いました。それまで営々と続いていた茶(清→イギリス)と綿織物(イギリス→インド)とアヘン(インド→清)の三角貿易の関係が、清によるアヘンの拒絶と、イギリスによる茶の獲得によって瓦解していきます。
その「茶を盗み出す」という重大な役割を請け負った、ロバート・フォーチュンというスコットランド人の物語です。
プラントハンターとは、その名の通り植物を狩る人たちで、他国へ行き、現地の有用な植物を「発見」し、目録を作り、種や苗を自国(または植民地)へ運ぶのが仕事です。
運んだ先でその植物が産業化されれば、原産地から輸入する事なく獲得出来るとともに自国が潤います。
バナナ、サトウキビなどがその例としてあげられていますが、多くの園芸植物、農産物がハンティングされました。これは産業スパイに他なりません。
読み進むうちに、学校で習い覚えのあった「プランテーション」という言葉が、生々しいイメージとともに再認識されました。
「茶を盗む」と聞きますと、闇夜に電光石火の早業で、こっそり一握りの種を隠して颯爽と立ち去る、、そんなシーンを想像しましたが、全然違いました。
種も苗も万の数を船で輸送するのです。これをスコットランド人が中国人に扮装して潜入して行うにはいささか無謀に見えます。
sawaromaさんは「"007の国イギリス"を見た」とかかれていましたが、無謀な計画を命の危険がありながらやり遂げるところは確かに読みごたえがありますね。
もうひとつの主人公「お茶」に焦点を絞れば、フォーチュンが「緑茶」と「烏龍茶」(本では紅茶として書かれています)を盗んだこと、フォーチュンが中国で着色していることを紹介するまではイギリスでは緑茶が飲まれていた事などが興味深いです。
中国茶が好きな私としては、武夷の烏龍茶がダージリンの紅茶になっていく過程なども知りたい所ですが、それはこの物語の趣旨とは違いますね。
植物が世界を変える原動力になる、一人のスパイが国の運命すら左右する、、この表現が誇張ではない事が感じられる本です。
sawaromaさん、ありがとうございました!
sawaromaさんブログ:サラ・ローズ著「紅茶スパイ 英国人プラントハンター中国をゆく」(原書房)
http://sawaroma.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
1ヶ月ほどかけて読みましたが、ノンフィクションはいつにもまして時間が掛かってしまうので、私にしては速かったと思います。
19世紀半ば、清とイギリスはアヘン戦争を戦いました。それまで営々と続いていた茶(清→イギリス)と綿織物(イギリス→インド)とアヘン(インド→清)の三角貿易の関係が、清によるアヘンの拒絶と、イギリスによる茶の獲得によって瓦解していきます。
その「茶を盗み出す」という重大な役割を請け負った、ロバート・フォーチュンというスコットランド人の物語です。
プラントハンターとは、その名の通り植物を狩る人たちで、他国へ行き、現地の有用な植物を「発見」し、目録を作り、種や苗を自国(または植民地)へ運ぶのが仕事です。
運んだ先でその植物が産業化されれば、原産地から輸入する事なく獲得出来るとともに自国が潤います。
バナナ、サトウキビなどがその例としてあげられていますが、多くの園芸植物、農産物がハンティングされました。これは産業スパイに他なりません。
読み進むうちに、学校で習い覚えのあった「プランテーション」という言葉が、生々しいイメージとともに再認識されました。
「茶を盗む」と聞きますと、闇夜に電光石火の早業で、こっそり一握りの種を隠して颯爽と立ち去る、、そんなシーンを想像しましたが、全然違いました。
種も苗も万の数を船で輸送するのです。これをスコットランド人が中国人に扮装して潜入して行うにはいささか無謀に見えます。
sawaromaさんは「"007の国イギリス"を見た」とかかれていましたが、無謀な計画を命の危険がありながらやり遂げるところは確かに読みごたえがありますね。
もうひとつの主人公「お茶」に焦点を絞れば、フォーチュンが「緑茶」と「烏龍茶」(本では紅茶として書かれています)を盗んだこと、フォーチュンが中国で着色していることを紹介するまではイギリスでは緑茶が飲まれていた事などが興味深いです。
中国茶が好きな私としては、武夷の烏龍茶がダージリンの紅茶になっていく過程なども知りたい所ですが、それはこの物語の趣旨とは違いますね。
植物が世界を変える原動力になる、一人のスパイが国の運命すら左右する、、この表現が誇張ではない事が感じられる本です。
sawaromaさん、ありがとうございました!
sawaromaさんブログ:サラ・ローズ著「紅茶スパイ 英国人プラントハンター中国をゆく」(原書房)
http://sawaroma.blogspot.com/2012/01/blog-post.html


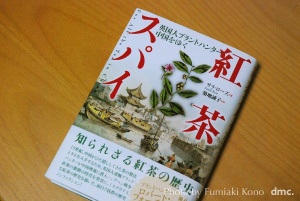

最近のコメント