「カメのきた道」 ― 2013年05月21日 23:41
特に亀を専門とされる化石爬虫類学者、平山廉氏の著書「カメのきた道」です。
帯の「甲羅というシェルターとスローな生き方という第三の戦略を選んだカメたち」というコピーに惹かれて読みました。
第一の戦略とは爬虫類の「大型化と効率化」、第二の戦略はほ乳類の「小型化と連続エネルギー補給による活発化」のことで、カメの戦略は「非大型化と効率化」だそうです。
捕食以外はじっとして大きく育つ爬虫類、せわしなく動き回り世代交代を重ねて行くほ乳類、代謝を抑えて少しの食料で長く生きるカメ、、といったイメージでしょうか?
現生のカメの特徴と仕組み、多様な環境に進出した適応、謎だらけの起源、海への進出、恐竜時代からほ乳類時代にかけて生き延びた事実、最悪の捕食者人間とのかかわり、、学者の説く淡々とした事実認識にいつの間にか惹きつけられて、最後まで面白かった!
興味深い事に、恐竜の大量絶滅など何度かあった地球全体の淘汰時期にも、カメは影響を受けずに生き延びているのだそうです。(もちろん種毎の根絶は他の生き物同様ありますが)
有史以来もっともカメを絶滅させたのはやはり人間なのですが、何千万年かした後のほ乳類の時代が終わった時にも、カメはその戦略によって生き残っている可能性を感じました。
読み進むにつれだんだんカメが飼いたくなってきたのですが、最後の最後で「ペットには向いていないと思う」とあります。
何故かと言いますと「飼い主より長生きするから」。なるほど!無責任に飼うことはできないですよね。(でもやはり飼ってみたいです・・)
ところで、本書では触れられていませんが「大型で活発」という第四の戦略をとった生物もかつていました。恐竜ですね。肺をもつ生物の約二倍の酸素摂取効率で巨体を高速で動かして捕食していました。(ピーター・D. ウォード著「恐竜はなぜ鳥に進化したのか」に詳しく書かれています。)
温暖化して酸素濃度が下がるとほ乳類(特に大型)は生きられなくなるそうですが、その時でも恐竜の生き残りである鳥と効率化の進んだカメは生き延びていそうです。
まさしく「鶴は千年、亀は万年」なのですね。
過去記事:「恐竜はなぜ鳥に進化したのか」
http://dmc.asablo.jp/blog/2010/09/24/
帯の「甲羅というシェルターとスローな生き方という第三の戦略を選んだカメたち」というコピーに惹かれて読みました。
第一の戦略とは爬虫類の「大型化と効率化」、第二の戦略はほ乳類の「小型化と連続エネルギー補給による活発化」のことで、カメの戦略は「非大型化と効率化」だそうです。
捕食以外はじっとして大きく育つ爬虫類、せわしなく動き回り世代交代を重ねて行くほ乳類、代謝を抑えて少しの食料で長く生きるカメ、、といったイメージでしょうか?
現生のカメの特徴と仕組み、多様な環境に進出した適応、謎だらけの起源、海への進出、恐竜時代からほ乳類時代にかけて生き延びた事実、最悪の捕食者人間とのかかわり、、学者の説く淡々とした事実認識にいつの間にか惹きつけられて、最後まで面白かった!
興味深い事に、恐竜の大量絶滅など何度かあった地球全体の淘汰時期にも、カメは影響を受けずに生き延びているのだそうです。(もちろん種毎の根絶は他の生き物同様ありますが)
有史以来もっともカメを絶滅させたのはやはり人間なのですが、何千万年かした後のほ乳類の時代が終わった時にも、カメはその戦略によって生き残っている可能性を感じました。
読み進むにつれだんだんカメが飼いたくなってきたのですが、最後の最後で「ペットには向いていないと思う」とあります。
何故かと言いますと「飼い主より長生きするから」。なるほど!無責任に飼うことはできないですよね。(でもやはり飼ってみたいです・・)
ところで、本書では触れられていませんが「大型で活発」という第四の戦略をとった生物もかつていました。恐竜ですね。肺をもつ生物の約二倍の酸素摂取効率で巨体を高速で動かして捕食していました。(ピーター・D. ウォード著「恐竜はなぜ鳥に進化したのか」に詳しく書かれています。)
温暖化して酸素濃度が下がるとほ乳類(特に大型)は生きられなくなるそうですが、その時でも恐竜の生き残りである鳥と効率化の進んだカメは生き延びていそうです。
まさしく「鶴は千年、亀は万年」なのですね。
過去記事:「恐竜はなぜ鳥に進化したのか」
http://dmc.asablo.jp/blog/2010/09/24/
状態をセンシング「Touché(トゥーシェ)」 ― 2013年05月22日 14:31
ディズニーが開発発表したタッチセンシング技術が凄いと訊いて動画を拝見。
面白いですねぇ。アイデア自体は慣れ親しんだものの延長に感じますが、「空中でのジェスチャーではなく、具体物への接し方」の意味を電気的に捉えられるのは素晴らしいと思います。
一つには画像処理ではなく、センサーの入力パターンの処理なので、小型化や低コストか等色々と有利そうです。
もう一つには、以前にも触れておりますが、人へのフィードバックと周囲への気配が明確なことです。これはとても大きな意味があると思っています。
まずはディズニーワールドで体験出来るようになるのでしょうか?楽しみです。
紹介記事:ディズニーが開発したタッチセンサーの新技術「Touché」がまさにイノベーション
面白いですねぇ。アイデア自体は慣れ親しんだものの延長に感じますが、「空中でのジェスチャーではなく、具体物への接し方」の意味を電気的に捉えられるのは素晴らしいと思います。
一つには画像処理ではなく、センサーの入力パターンの処理なので、小型化や低コストか等色々と有利そうです。
もう一つには、以前にも触れておりますが、人へのフィードバックと周囲への気配が明確なことです。これはとても大きな意味があると思っています。
まずはディズニーワールドで体験出来るようになるのでしょうか?楽しみです。
紹介記事:ディズニーが開発したタッチセンサーの新技術「Touché」がまさにイノベーション
ワープロ修理の専門店 3Dの未来 ― 2013年05月23日 23:45
手書き看板の「パソコン試してワープロの優しさを知る」が味を出してるこのお店は、ワープロ修理の専門店だそうです。なんと創業1953年!(もちろん創業時は街の電気屋さんだったのでしょうけれど)
私は昨年タイプライターと時計の修理先を探しましたが、使い慣れた、もしくは思い出深い道具は直したいと思います。そういう方が増えているとも聞きます。
近い将来、一般の方々にとって3Dプリンティングがもっとも身近になるのはこう言う修理やカスタマイズショップかもしれませんね。カラーレーザーが普及したのは数百万台前半になった時だったとのことなので、修理実用に耐える性能の物がその価格帯になるのは1〜2年後くらいでしょうか?楽しみです。
私は昨年タイプライターと時計の修理先を探しましたが、使い慣れた、もしくは思い出深い道具は直したいと思います。そういう方が増えているとも聞きます。
近い将来、一般の方々にとって3Dプリンティングがもっとも身近になるのはこう言う修理やカスタマイズショップかもしれませんね。カラーレーザーが普及したのは数百万台前半になった時だったとのことなので、修理実用に耐える性能の物がその価格帯になるのは1〜2年後くらいでしょうか?楽しみです。
てづくりの未来 ― 2013年05月24日 23:59

知人の手作りジャムがもの凄く美味しくて、「ジャムってこんなに美味しいんだ!」と感動しておりましたが、そのジャムが晴れて正式なブランドになりました。
明日は「ヨコハマハンドメイドマルシェ2013」にて、そのプレスタートだそうです。
イベント日和の週末、沢山の方にあの美味しさを知って欲しいと思います。
みなさん、みなとみらいに行かれたら是非パシフィコまで足を伸ばして見て下さい!
ところで、修理とカスタマイズが最新技術で盛んになりそう、ということを昨日書いたのですが、「てづくり」はどうなっていくのでしょうね?
昨日の延長では「MAKERS」ももちろん魅力的なのですが、こちらはどちらかというとパーソナルブランド自身による贔屓との長い付きあい、のようなスタイルを想像します。それは幸せな消費だと思います。
(そう思いますと、このマルシェは既に日本版「Etsy」を想定したものなのかもしれません)
A+ Confiture / アプリュス・コンフィチュール
https://www.facebook.com/AplusConfiture
ヨコハマハンドメイドマルシェ2013
http://handmade-marche.jp/
Etsy
http://www.etsy.com/
明日は「ヨコハマハンドメイドマルシェ2013」にて、そのプレスタートだそうです。
イベント日和の週末、沢山の方にあの美味しさを知って欲しいと思います。
みなさん、みなとみらいに行かれたら是非パシフィコまで足を伸ばして見て下さい!
ところで、修理とカスタマイズが最新技術で盛んになりそう、ということを昨日書いたのですが、「てづくり」はどうなっていくのでしょうね?
昨日の延長では「MAKERS」ももちろん魅力的なのですが、こちらはどちらかというとパーソナルブランド自身による贔屓との長い付きあい、のようなスタイルを想像します。それは幸せな消費だと思います。
(そう思いますと、このマルシェは既に日本版「Etsy」を想定したものなのかもしれません)
A+ Confiture / アプリュス・コンフィチュール
https://www.facebook.com/AplusConfiture
ヨコハマハンドメイドマルシェ2013
http://handmade-marche.jp/
Etsy
http://www.etsy.com/
ロボットのOSは日本語が最適? ― 2013年05月27日 11:10
昨日、企業に派遣されて外国人に日本語を教える仕事をされている方から「日本語は場面型言語」というお話を伺いました。
同音多義が多く助詞により意味が変わる日本語は、「場面」で捉えることで判りやすくなるそうです。いわゆる文脈依存型の言語と言う事なのだと思いますが、「文脈」ではなく「場面」でというのが実践的なのでしょう。
(検索では見当たりませんでしたから、その方の造語かも知れません)
話は飛びますが、人工知能の難題に「フレーム問題」というのがあります。無限に考えられる状況から最適な選択肢を選ぶのは時間が掛かってしまうため、有限の状況(=フレーム)を用意するが、最適なフレームを選ぶにも時間が掛かる、というものです。
人とシステムのUIのひとつの完成系としては、やはり言語によるコミュニケーションだと思いますから、状況把握を前提とした言語でOSを作ると面白いのでは?
・・「場面型言語」という言葉を伺って、素人の思いつきではありますが、そんなことを夢想しました。
WIKIPEDIA:フレーム問題
http://ow.ly/lpRPK
同音多義が多く助詞により意味が変わる日本語は、「場面」で捉えることで判りやすくなるそうです。いわゆる文脈依存型の言語と言う事なのだと思いますが、「文脈」ではなく「場面」でというのが実践的なのでしょう。
(検索では見当たりませんでしたから、その方の造語かも知れません)
話は飛びますが、人工知能の難題に「フレーム問題」というのがあります。無限に考えられる状況から最適な選択肢を選ぶのは時間が掛かってしまうため、有限の状況(=フレーム)を用意するが、最適なフレームを選ぶにも時間が掛かる、というものです。
人とシステムのUIのひとつの完成系としては、やはり言語によるコミュニケーションだと思いますから、状況把握を前提とした言語でOSを作ると面白いのでは?
・・「場面型言語」という言葉を伺って、素人の思いつきではありますが、そんなことを夢想しました。
WIKIPEDIA:フレーム問題
http://ow.ly/lpRPK
空気の手応え FFB(フォースフィードバック) ― 2013年05月28日 11:39
以前の記事で、「そろそろFFB(フォースフィードバック)の技術が盛んになるのではないかと思っています。」と書きましたが、今日こんな動画が上がっているのを見つけました。
今年のシーグラフのハイライト動画の中で、46秒頃から「AIREAL」が紹介されています。高速で移動するユーザーの手にめがけてエアーを噴射する技術です。「手応え」を演出しようと言う訳ですね。
ディズニーの研究所だそうですが、先日紹介した「Touché」もディズニーでしたね。
空気の演出はディズニーランドのアトラクションで経験されたことがある方は多いでしょう。その家庭版が画期的という訳ですね。
空気噴射と言えば、随分前から視覚障害者向けのインフォメーションとしてのアイデアを聞いていますが、なかなか見かける事がありません。
もしコストや特別な技術などの問題なら、この家庭用の技術からの転用で充分なシステムが作れそうです。
どなたか一緒にデザインしませんか!?
紹介記事:Kinectでのプレイを「空気」のフィードバックでもっと面白く。ディズニー・リサーチが技術開発
今年のシーグラフのハイライト動画の中で、46秒頃から「AIREAL」が紹介されています。高速で移動するユーザーの手にめがけてエアーを噴射する技術です。「手応え」を演出しようと言う訳ですね。
ディズニーの研究所だそうですが、先日紹介した「Touché」もディズニーでしたね。
空気の演出はディズニーランドのアトラクションで経験されたことがある方は多いでしょう。その家庭版が画期的という訳ですね。
空気噴射と言えば、随分前から視覚障害者向けのインフォメーションとしてのアイデアを聞いていますが、なかなか見かける事がありません。
もしコストや特別な技術などの問題なら、この家庭用の技術からの転用で充分なシステムが作れそうです。
どなたか一緒にデザインしませんか!?
紹介記事:Kinectでのプレイを「空気」のフィードバックでもっと面白く。ディズニー・リサーチが技術開発
固有感覚のUI ― 2013年05月29日 23:56
五感以外の感覚、いわゆる第六感とは「見えないものが見えてしまう」というものではなくて、固有感覚(運動感覚・身体感覚)のことだそうです。
自分の体がどうなっているか判る感覚のことですね。これが「感覚」にリストアップされなかったのは、自分自身である認識は感覚のベースと言えるからなのでしょう。そう思うと第六感ではなく第零感がふさわしいのかも。
この固有感覚、視覚や聴覚等の五感同様にデザインとの関わりがありますでしょうか?・・と思って見回しますと、いわゆる「道具の身体化」がありました。
バットや刃物といった道具から自動車や顕微鏡手術装置のような機械まで、自分の手足の延長のように感じて扱う「名人芸」「ゴッドハンド」は、訓練を通じて固有感覚が身体外まで拡張させたとイメージする事が出来ます。
また、セグウェイや介助補助装具(身体の外側に装着して力仕事を補う)のように、直接的に身体能力を拡張するものは、同時に固有感覚も拡張しているでしょう。
これは面白いなぁと思います。
一般にUI(ユーザーインターフェイス)には人とシステムの「対話」がベースにあります。「自然なUI」と形容されるタッチUIや研究中の「タンジブル」もそうですね。
しかし固有感覚を拡張するようなシステムは対話ではありません。対話している時間も、対話に必要なシステムとの関係性を意識する事も邪魔になります。
対話ではなく拡張、ですね。
UIの発展系としてUX(ユーザーエクスペリエンス:経験)が定着していますが、これが(一般的に言われる様に)ストーリーのデザインだとしたら、UXは対話型のインターフェイスに近いと言えそうです。
しかし、ストーリーを離れて、もっと本来の意味で「経験」を考えますと、固有感覚を拡張される方が遥かに面白いはずです。
前者を「特殊能力を持ったシステムを使いこなす経験」としますと、後者は「自身の身体に特殊能力が宿るような経験」と言えるでしょう。(理想的には、ですけれど)
身体感覚の拡張自体は既に沢山の前例がありますが、そこに「自動化」の視点にたってみますと、ひとつの形がありそうです。わくわくしてきました。
自分の体がどうなっているか判る感覚のことですね。これが「感覚」にリストアップされなかったのは、自分自身である認識は感覚のベースと言えるからなのでしょう。そう思うと第六感ではなく第零感がふさわしいのかも。
この固有感覚、視覚や聴覚等の五感同様にデザインとの関わりがありますでしょうか?・・と思って見回しますと、いわゆる「道具の身体化」がありました。
バットや刃物といった道具から自動車や顕微鏡手術装置のような機械まで、自分の手足の延長のように感じて扱う「名人芸」「ゴッドハンド」は、訓練を通じて固有感覚が身体外まで拡張させたとイメージする事が出来ます。
また、セグウェイや介助補助装具(身体の外側に装着して力仕事を補う)のように、直接的に身体能力を拡張するものは、同時に固有感覚も拡張しているでしょう。
これは面白いなぁと思います。
一般にUI(ユーザーインターフェイス)には人とシステムの「対話」がベースにあります。「自然なUI」と形容されるタッチUIや研究中の「タンジブル」もそうですね。
しかし固有感覚を拡張するようなシステムは対話ではありません。対話している時間も、対話に必要なシステムとの関係性を意識する事も邪魔になります。
対話ではなく拡張、ですね。
UIの発展系としてUX(ユーザーエクスペリエンス:経験)が定着していますが、これが(一般的に言われる様に)ストーリーのデザインだとしたら、UXは対話型のインターフェイスに近いと言えそうです。
しかし、ストーリーを離れて、もっと本来の意味で「経験」を考えますと、固有感覚を拡張される方が遥かに面白いはずです。
前者を「特殊能力を持ったシステムを使いこなす経験」としますと、後者は「自身の身体に特殊能力が宿るような経験」と言えるでしょう。(理想的には、ですけれど)
身体感覚の拡張自体は既に沢山の前例がありますが、そこに「自動化」の視点にたってみますと、ひとつの形がありそうです。わくわくしてきました。
ドバイ24時間 ― 2013年05月30日 23:48
ロシアのカメラマンDimidさんのドバイのタイムラプスムービーです。
超巨大でどこまでも人工的美で埋め尽くされた世界、、不思議な美しさです。
Dubai Timelapse from dimid on Vimeo.
超巨大でどこまでも人工的美で埋め尽くされた世界、、不思議な美しさです。
ひとつ新しいのがでます! ― 2013年05月31日 23:10
来週、6月5日から7日まで開催される「インテリアライフスタイル東京」で、新しいデザインをひとつ、皆さまにご披露させて頂くことになりました!
ご来場の際は「アッシュコンセプト」さまのブースを覗いてみて下さい!
詳細は後日改めまして、ご報告させて頂きます。
http://www.interior-lifestyle.com/
ご来場の際は「アッシュコンセプト」さまのブースを覗いてみて下さい!
詳細は後日改めまして、ご報告させて頂きます。
http://www.interior-lifestyle.com/


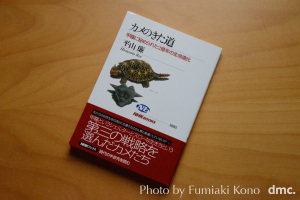


最近のコメント