「いれもの」 ― 2010年06月15日 23:59
またまた嬉しいお便りを、ミサリングファクトリーの松本さんから頂きました。
ご紹介させて頂きます。
ミサリングファクトリーでは、子ども向けにお菓子作りを教えていますので、小さいお子さんを持つお母さんも沢山集まっています。
そのお母さんたちがミチクサを大変気に入って下さっていると。
伺いますと、子どもが摘んでくる花を活けるのだそうです。
「ママ〜、これあげる!」と公園のツメクサやたんぽぽを持ってきてくれる花をコップに活けた事のある方は多い事でしょう。
それをミチクサに変えて、食卓に飾って下さっているのです。
もちろん、この喜びはどんな花器だろうと関係ありません。
でもそれを、少しでも長く楽しむ事ができたら、それはとても幸せなことでね。
先日ご紹介したエピソードもそうでしたが、私がミチクサに込めた思いとは別の、本当の物語が備わってくれている。そのことが本当に嬉しいのです。
ところで、感動の記憶がまだ新しい「はやぶさ」も、私を含め多くの方が機械を越えた命的なものをその中に見ています。エンジニアたちが全魂を込めたプロジェクトは、その思いを遥かに越えて、多くの感動を呼びました。
私のデザインと「はやぶさ」を並べる事自体、大変おこがましいのですが、私の中ではひとつのイメージが浮かびました。
それは「いれもの」というイメージです。
私はデザインの中に「メッセージを込める」という事が、絶対的に必要だとは思いながら、何かその恣意性に違和感を覚えていました。
しかしそうではないのです。思いを受止める入れ物を作っておいて、そこに思いやメッセージを詰めておく。
それがお客様の手に渡ったら入れ物の詰め物は取除かれ、お客様にとっての思いやメッセージを詰めて頂くのです。
これが「込めるということなのだ」、と一人ごちています。
松本さん、ありがとうございました!
躑躅(つつじ)と匂蕃茉莉(においばんまつり)。
X6 雑感 ― 2010年06月16日 23:59
まず本体の写真です。
これは待受け画面。下部のアイコンはショートカットです。
すっきりした背面。私はこの背面が好きです。
ダブルフラッシュは強力で、12平米8畳間程度なら部屋の隅まで明るく撮れました。(サンプルは残念ながら初期化の際に消失)
-タッチUIの危うさ-
携帯電話として歴史も台数も実績と厚みのあるメーカーが、タッチUIを作るとどうなるのだろう。。
これが一番感じたい部分でした。これは私なりの答えが出るほど使う時間があったとは言えませんのであくまで第一印象なのですが、正直を申し上げれば「使えるけれど特別な感情は湧かなかった」といえます。
繰返して恐縮ですが、これは第一印象ですので長時間使うとまた変わってくるかも知れません。
タッチデバイスの感度と精度は、以前からタッチUIの課題でした。その点でX6は良く出来ていると感じました。軽いタッチでもしっかりと操作を受け付けていました。
ただし、一部のユーザーは求めるレベルがとても高いのです。従って「期待に応えているか」という観点からすると評価が分かれる所でしょう。期待に応えられなければ返って評価を落としてしまいますね。
ですから、「そこそこのタッチUI」なら、その機器のユーザーの期待をよくよく鑑みて採用を再検討するべきかも知れません。
-単体の魅力-
X6はカメラ、音楽、動画、GPS等の各種機能性能は上位クラスです。アプリケーションも日本語化されたものは少ないのですが、定番のものは多く存在します。
またNOKIAには、X6同等のスペックのハードウエアが沢山存在します。UIやスタイルも豊富です。
ユーザーにとってはプロダクトの仕様とともに、ハードウェアデザイン、カラーバリエーション、グラフィックデザインが選べることはいい事だと感じるでしょう。自分の好みに遭った魅力的なモノを見つけられる可能性が高いのてすからね。
また、PCとの連携はスマートフォンでは必須ですが、「携帯電話プラス」の範囲なら不要です。
PCにもキャリアのサービスに依存せずに新機種に引越が出来るのは素晴らしいですね。
N82からX6へBluetooth経由で引越。電話帳はもちろんブックマークやコンテンツも。
メールボックスの設定が移せなかったのは残念。
-プラットフォーム-
今でも通信の規格に深く関わっているNOKIAは、何年か前まではモバイルの開発者が最も集まっていたはずで、プラットフォーマーとして覇権を握り続けると思われていました。しかし今のトレンドは少し違うようです。
それは「アプリケーション」とその流通ですね。優れたアプリケーションが集まってこないプラットフォームはユーザーの期待に応えられないのです。
ですから、プラットフォーマーとしての勝敗は、ユーザーのメリットに直結していると言えますね。「ネットとアプリケーションの豊富な世界へ繋がっている」という感覚をユーザーに提供し続けるためには、大胆な方針転換が必要かも知れません。
これはNOKIAは得意なはずで、期待したいと思います。
ほんの数日でしたが、実際に触る事で色々なことを感じ、それまで考えていたことの確認や、新しい着想の切掛を得る事が出来ました。
夏! ― 2010年06月17日 18:05
「心は実験できるか」 ― 2010年06月18日 23:59
ローレン・スレイター著「心は実験できるか」2005年
心理学者を野心的な存在として捉え、当時の社会的背景との対比で浮かび上がらせる書き味がスリリングで、読み物としてとても面白いです。
(詳細はレビューを参照して下さい。)
デザインをする上で、人の心理の理解はとても大切だと考えています。一人のユーザーと一つの機器の間、一対一の関係を丁寧に作るためには、人への理解が大切なのは言うまでもありません。
また、私たちは実際には集団の中で生活していますから、一対一の関係同様に、集団の中での心の働きへ、関心と理解が必要なのだと考えています。
ここで大切なのは、一対一のときはデザイナー自身の感性、気付きがとても大切だと言う事。
そしてもう一つ、集団のときは個人の感覚よりも客観的な観察による気付きが大切だ、と言う事です。
どちらも大切です。
ご紹介した本は、集団への関心を充分に惹きつけてくれる一書です。
素材を替える ― 2010年06月21日 23:28
インターフェイスデザインの中で良く使われる概念の中に「アフォーダンス」があります。
良く使われる喩えですが、ドアノブの形は、握って回す動作を促しています。これは私たちがその形態に「意味」を感じているからで、アフォーダンスとはその意味の事です。
アフォーダンスは形態だけではなく、素材にも感じとる事が出来ます。
例えば、金属で出来ている扉は力を込めて開けます。「重さ」を感じているからですね。
何を当り前なことを、とお思いかもしれませんが、これは重要な事です。
たとえば、既存製品の素材を新しくする事で性能を伸ばす開発の様な時、単なる置きかえでは問題があるかもしれません。アフォーダンスが変わると言う事は行為が変わってきますから、形態や時には仕様まで確認を必要とします。
デザイナーはこの「意味」について、責任を持って説明をする必要があるでしょう。
また、素材を変える事でアフォーダンスが変わる、という事を積極的に行為へのアプローチとして活用したいと考えています。
良く使われる喩えですが、ドアノブの形は、握って回す動作を促しています。これは私たちがその形態に「意味」を感じているからで、アフォーダンスとはその意味の事です。
アフォーダンスは形態だけではなく、素材にも感じとる事が出来ます。
例えば、金属で出来ている扉は力を込めて開けます。「重さ」を感じているからですね。
何を当り前なことを、とお思いかもしれませんが、これは重要な事です。
たとえば、既存製品の素材を新しくする事で性能を伸ばす開発の様な時、単なる置きかえでは問題があるかもしれません。アフォーダンスが変わると言う事は行為が変わってきますから、形態や時には仕様まで確認を必要とします。
デザイナーはこの「意味」について、責任を持って説明をする必要があるでしょう。
また、素材を変える事でアフォーダンスが変わる、という事を積極的に行為へのアプローチとして活用したいと考えています。
結局、マグより水筒 ― 2010年06月22日 21:52
水筒や携帯マグカップ(タンブラー)はすっかり日常の定番となりましたね。
詳細の経緯はわかりませんが、コーヒーショップのマグが「ドリンクを持ち歩く」事を日常化して、その後エコや節約などの価値観に後押しされたような印象を持っています。
コーヒーを一日7杯は飲み、中国茶の大好きな私にとって、このトレンドは嬉しい限り。マグやボトルが様々なスタイル、デザイン、機能、サイズのものが市場に出ていて見るだけでも楽しいです。
私がこれまで使用したものは、、
・ショップオリジナルのマグ(3点〜)
→グラフィックの楽しさに惹かれて。
・ステンレス二重マグ(1点)
→質感の高さと機能に期待して購入。
・高性能蓋マグ(1点)
→蓋の機能性を期待して。
・アルミボトル(1点)
→軽さの魅力と携帯性(キャップがフックできる形状)で。
・真空二重水筒(2点)
→機能性の高さで。
・・・結構使ってますね!
上記は全部蓋が付いたもので、使用した順は前後しています。念のため。
コーヒーショップのオリジナルマグは、デザインの楽しさが魅力ですね。
私もいくつか買っています。オリジナルのグラフィックを入れられるものは人にも配ったりしました。(おばあちゃんに孫の写真を入れて、等)
保温性や密閉性は期待出来ませんが、気分を変えてくれるのは嬉しい事です。
ステンレス二重のマグは、ステンレスの質感と機能性にマグの楽しさの両方を求めました。
しかし実際使用してみると、機能よりデザインを楽しむもののようです。真空二重のものでないと、中の温度がダイレクトに手に伝わるんですね。重たさも高級感ではありますが、携帯性にはやや不利です。
ただし、質感の高さは素晴らしく、時々気が向くと使っています。
高性能蓋のマグは、ワンプッシュで開閉出来て飲み口も工夫されたものです。本体も樹脂の二重構造でグリップの良さなど様々な機能を追求したものでした。
機能性は確かに素晴らしくバランスもいいと感じました。
ただ、容量に対して大き過ぎるのが残念な印象でした。デザインも機能的なので、好き嫌いが分かれるかもしれません。
アルミボトルは、できるだけ軽く持ち歩く、という意味でアウトドア向きです。この軽さは素晴らしいです。
ただし常温のものに限られるので、日常向きではないかもしれません。
真空二重水筒は、そのコンパクトさと保温性の高さが魅力です。真夏の朝に入れた氷が夕方まで残っているのは感動的に嬉しいのです。それだけで真空二重の素晴らしさを実感出来ます。それも小さくて軽いのです。
保温がしっかりしていると言うのは、熱や水滴の心配がいらないので、それもいいですね。
そしてもうひとつ見逃してはいけないポイントがありました。それは「密閉性」です。
アルミボトルと水筒は今まで一度も漏れていません。これがどれだけの安心感を生み、大切な機能かは、通年で使わないと判らない事でした。
「蓋が付いていれば漏れない」こう思うのは自然で、故に上記のどれもこぼれたりしないだろう、と当然のように思っていたのでした。しかし、蓋付きマグは長時間携帯しているとどうしても少しだけ漏れる事が、稀にあります。
この「少しだけ漏れるかもしれない」というのと「漏れない」の差は思っていた以上に大きかったのです。
真空二重水筒は「保温性」と「携帯性=省スペース+軽量+保温性+密閉性」で機能的に断トツです。
気に入ったデザインがあれば、ぜひ一度試して見て下さい!
2008年の秋からフルシーズン使用している水筒。
タイガー魔法瓶「SAHARA」0.3L
大分年季が入ってきました。
紅! ― 2010年06月23日 19:40
風化の大谷石 ― 2010年06月24日 23:45
大谷石は石垣などでみかける身近な石材です。(詳細はこちら)
子供の頃(昭和40年代/1970年代)、ご近所の石垣や石塀はみな大谷石だったかもしれません。
軽量で耐火性に優れ加工しやすいことから多用されたようですが、多孔質のため風化しやすい様です。私たちがよじ登るだけでもポロポロとよくに崩れていました。
風化で黒ずんで角は丸くなり、日陰では苔むした大きな穴にカタツムリがいて、小さい生物たちの住み家としても優しい印象が残っています。
時々崩れて真新しい淡い緑色が表れるのも好きでした。
最近はこの独特の素材感を求めて外壁に用いられているそうですが、風化の味わいを楽しむためには、ぜひとも厚めに使って頂きたいですね。
崩れて表れた大谷石の荒々しい表面。
プアなタッチUIでiPadを越えるには 考察の前に ― 2010年06月25日 23:59
インターフェイスデザインの現場では、ずっとこれを考え続けています。
数年前(正確には2007年)にiPhoneが発表されると、廃れる一方だったタッチUIは脚光を浴び、再び最先端でクールなものになりました。
この時、開発のロードマップを書き換えた機器は少なくなかったです。心臓部がコンピューターで、何らかのGUIを持ち、操作方法が機器の魅力の一部になっているものはみなさけて通れない課題でした。
中にはタッチでの勝負を最初から諦め、他の価値で勝負をしたものも多いと思います。機器によってはタッチを搭載すればそれでよしといったものもあったかもしれません。
この時の経験は、今からの波に備えて再認識と再評価をしておいた方がいいでしょう。
以前も書かせて頂きましたが、「タッチがあたりまえ」なユーザーに、プアなタッチUIを搭載した機器を、そのままで提供するのは、文字通り「丸腰で戦場へ向かう」ようなものでしょう。
本質論から言えば、素晴らしいタッチUIを開発するべきなのでしょう。また日本のメーカーの得意としてきた「ベンチマークより一歩も二歩も素晴らしいものを丁寧に作る」ことを、UIに向けて行けばいい事です。
しかし、それは現実的ではない、というのが正直な現状なのかもしれません。残念です。
それでは、タッチUIを含めてUIを実現するプラットフォームが不利なまま勝負をして行くにはどうすればいいのか。。
一つのヒントをiPhoneに求めたいと思います。
思い出しますと、iPhoneが出てくるまで、タッチUIは時代遅れなものでした。それがiPhoneによってどう昇華したのかを振り返ると、「直感的な操作」というコンセプトで、ただ「タッチ」するだけでなく、スライドさせたりピンチさせたりする方法を「自然で新鮮なもの」に仕上げていました。
今はレガシーで古くさいインターフェイスやデバイスも、同じ方法論が応用出来るかもしれませんね。
また、プロダクト自体が本来持っているインターフェイスを、再構築するのも有効な方法だと考えます。その機器に本当に画面が必要か、、これだけでも再考すればもっと自由な発想があるはずです。
以上、主語を曖昧にした書き方で恐縮ですが、どのような機器の開発でもさけて通れないと思っています。
具体的にお話出来る日が来る事を楽しみに、引続き考えて行きます!
感情移入 ― 2010年06月28日 12:57
私は小説が好きなのですが、主人公に感情移入して、一緒に一喜一憂し、物語を疑似体験する、、ありふれていますが、この「世界に浸る」感覚を、やっぱり味わいたいですね。
さて、商品を開発販売するにあたって、物語の重要性がよく言われますが、物語が購買に結びつくのは、この「感情移入」という行為が大きく関わっているのは間違いないでしょう。
そして、感情移入するのは「私にとって特別なもの」という商品だけではありません。
例えばメールやブログが面白くて「この人と話がしたいから買う」といってお客さんが集まるネットショップがあります。
また、非常に徹底した姿勢で商品を作り続ける職人を支援して「潰してはいけない」と遠方から集まるお店もあります。
貧困国の製品を、応援したい気持ちから積極的に購入する事例もしばしば耳にします。
「大切な商品」「大切な人」「大切なお店」「大切な機会」「大切なテーマ」と様々な側面で感情移入できるのですから、技術、商品、値段、スピード等々、それぞれはたとえ一番ではなくても、そのお客様にとっての「大切な何か」が提供できることで、愛して下さる商品、店舗になれるのですね。
当たり前のようで、この点を競争力として認識している方は案外少ないかも知れません。
私自身も含めて、作る人も売る人も買う人も、それぞれ固有の物語に感情移入できるかどうか、、ここが勝負です。
さて、商品を開発販売するにあたって、物語の重要性がよく言われますが、物語が購買に結びつくのは、この「感情移入」という行為が大きく関わっているのは間違いないでしょう。
そして、感情移入するのは「私にとって特別なもの」という商品だけではありません。
例えばメールやブログが面白くて「この人と話がしたいから買う」といってお客さんが集まるネットショップがあります。
また、非常に徹底した姿勢で商品を作り続ける職人を支援して「潰してはいけない」と遠方から集まるお店もあります。
貧困国の製品を、応援したい気持ちから積極的に購入する事例もしばしば耳にします。
「大切な商品」「大切な人」「大切なお店」「大切な機会」「大切なテーマ」と様々な側面で感情移入できるのですから、技術、商品、値段、スピード等々、それぞれはたとえ一番ではなくても、そのお客様にとっての「大切な何か」が提供できることで、愛して下さる商品、店舗になれるのですね。
当たり前のようで、この点を競争力として認識している方は案外少ないかも知れません。
私自身も含めて、作る人も売る人も買う人も、それぞれ固有の物語に感情移入できるかどうか、、ここが勝負です。












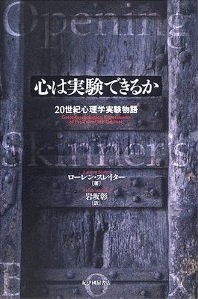





最近のコメント